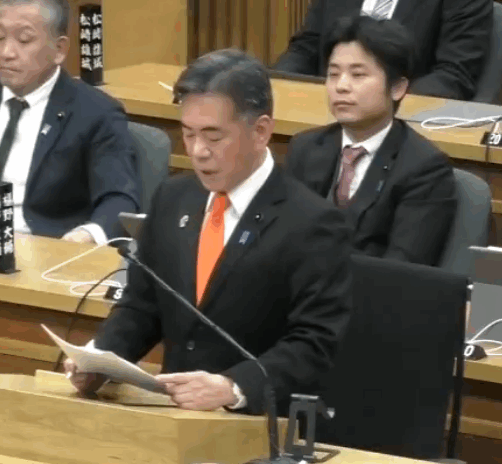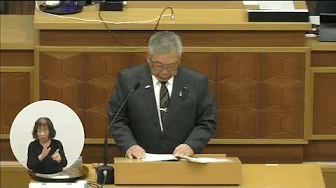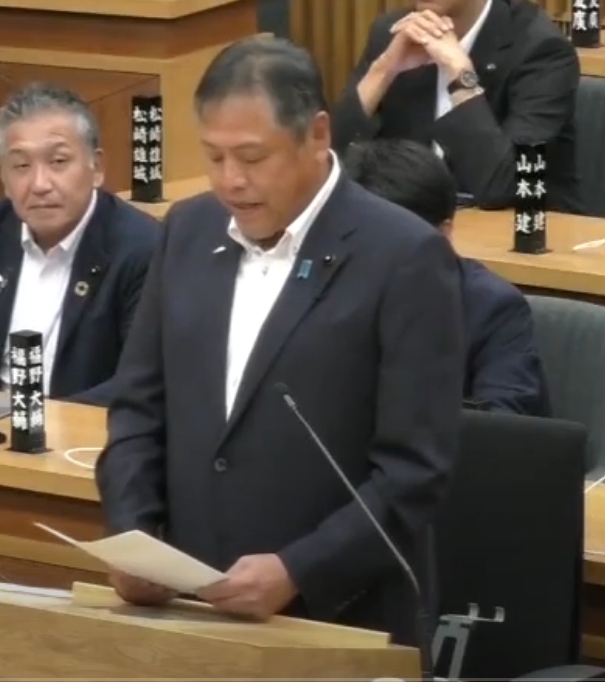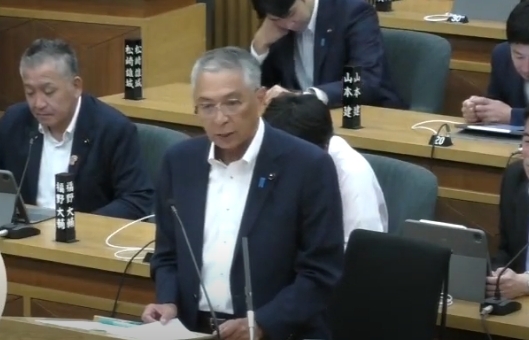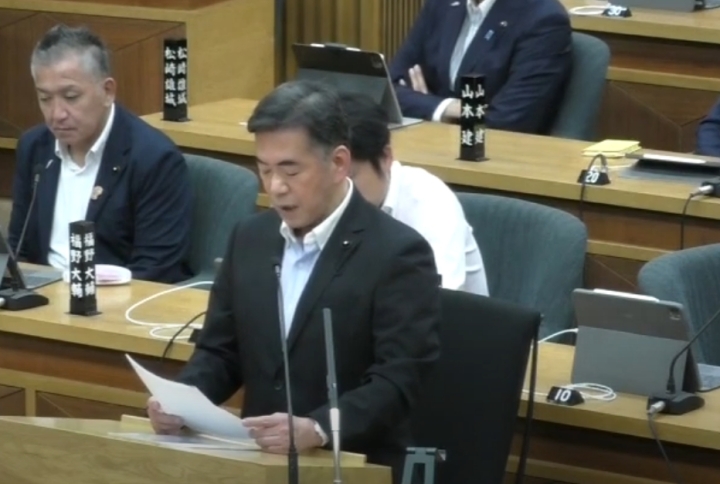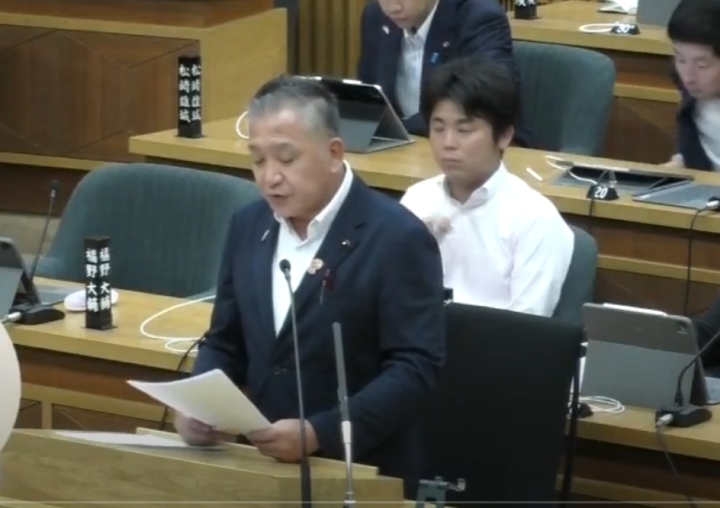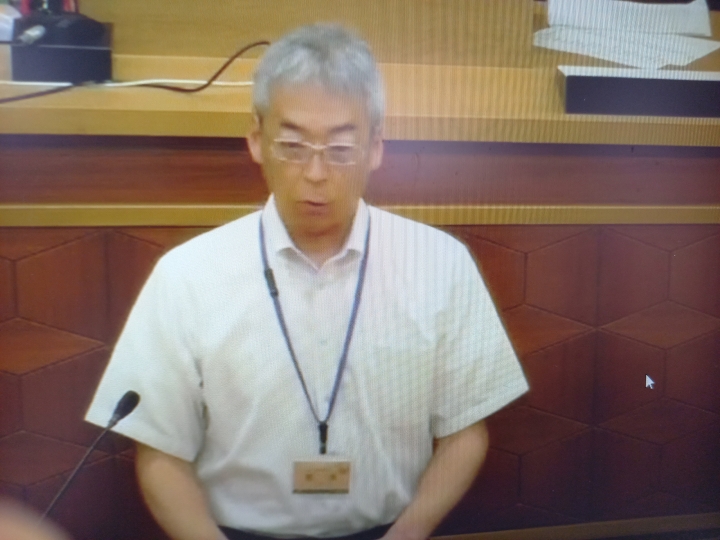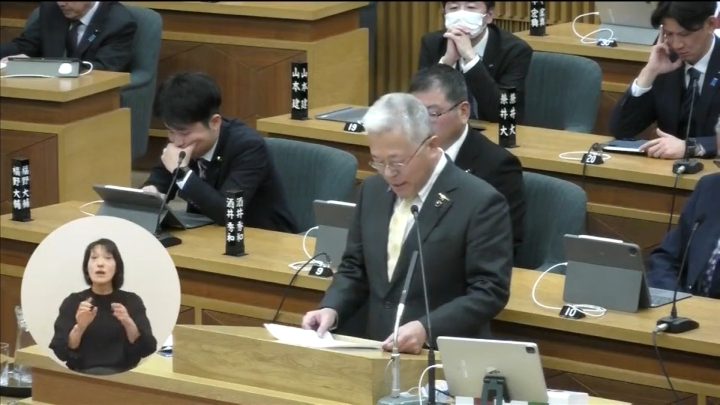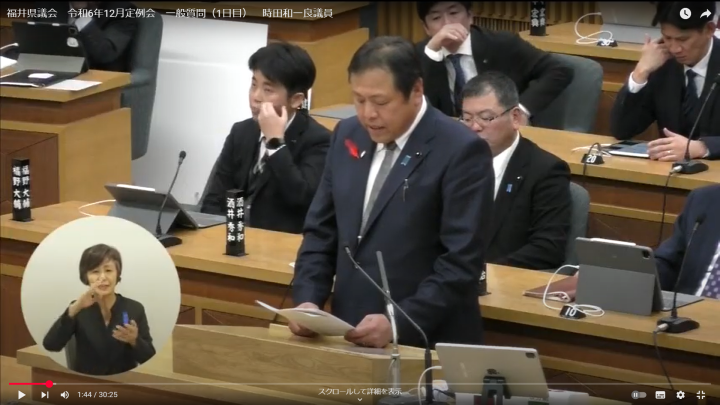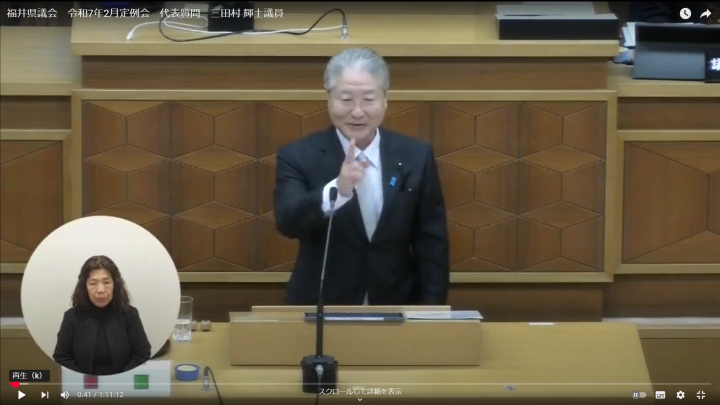令和7年12月10日 福井県議会本会議 一般質問
【学校給食の質の確保と有機食材、地場産食材・活用持続可能な農業の振興について】
学校給食の質の確保と、有機食材・地場産食材の活用、持続可能な農業の振 興についてを質問させていただきます。給食の無償化について、国は2026年度から月4700円程度の支援額を基準とする方向性を出 しております。 無償化していただくことはとてもうれしいことですが、自治体にも一定の負担を求めると いう方向で調整しているとのことで、自治体としては大変困った話でございます。 自治体によっては財源が限られており、物価高騰や米不足の影響を受ければ給食の質や量 が下がってしまう懸念がありますし、地産地消やオーガニックなど特色ある給食に取り組 んでいる地域ほど質が落ちてしまうのではないかとの不安の声が上がっております。 資料2を御覧ください。 そんな中、坂井市こどもの未来を考える会やさばえこどもまんなか環境給食推進委員会、 わかなえオーガニックプロジェクト、れおのわなど6団体が共同でオーガニック給食の推 進と給食の質確保に関する署名活動が行われまして、960名以上の署名が今集まっておりま す。 その署名と要望書を提出するために、私は現在県内の市町を回りまして、市町の担当者と 意見交換を行っているところでございます。 そこで、市町の様々な状況を知ることができ、国の無償化が始まることで自治体間の給食 の差がさらに広がるのではないかという危機感も感じているところでございます。 そこで質問いたします。 県として、市町が安定して質の高い給食、量を確保した給食を提供できるようにどのよう な支援を行うことができるとお考えでしょうか。 県として、国の支援に上乗せをしていただくことは可能でしょうか。 見解をお聞きいたします。 県として、市町の学校給食で有機米・特別栽培米の導入を支援する制度がございます。 有期米・特別栽培米を導入した際に発生した差額の3分の1を補助する制度でございます。 しかし、市町間で有機米導入の進み具合には大きな差があるようです。 有機米の導入ができない理由としては、「地元で有機米の供給量を十分に確保できない、 地産地消をやめてまで有期米に変える必要性を感じない」からだそうです。 有機米の生産者を増やし、供給量・価格ともに安定させるためには、県としてさらなる支 援が必要だなと感じております。 また、量は確保できているが、費用が問題という声もあり、補助額の拡大も必要と感じて おります。 さらに生産者からは、無農薬で作っているが、有機JASの認証を受けていないので補助 対象にならないという声もいただいております。 現状の制度では有機JAS認証米、または特別栽培米が補助対象だからです。 農水省や文科省の基準では、有機JAS認証を取得していなくても、「環境保全型農業直 接支払交付金」における「有機農業」の区分での交付金対象となっておれば、学校給食に おける有機産物として取り扱うことが可能となっております。 まずは昨今の米価高騰の状況もありますので、補助割合を現在の3分の1補助から、2分 の1補助に拡大できないか、また、補助対象についても拡大をお願いしたいと考えますが、 見解をお伺いいたします。また、有機農家の掘り起こしについては、県としてどのようなことができるとお考えでし ょうか。 新規就農者の育成・誘致、有機農業者による協議会の立ち上げ支援など、持続可能な農業 を広げるためにも県としてどのような取組が可能でしょうか。 有機米だけではなく、有機野菜への取り組みも含めてお伺いいたします。 県の市町への給食支援として、ほかには給食に地場産導入を推進する制度もございます。 現在、使用している食材にプラスして、地場産食材を追加した場合に補助が出る仕組みで ございます。 しかし、市町の担当者さんや栄養士さんからは***にしか使えなかったとかカレーにメンチカツを足す程度にしか使えなかったとか、そういった具体的な声もいただいておりま す。 それで、市町からは、プラスワンではなく、現在使用している食材を地場産に換える場合 にも対象にしてほしいということですが、導入のハードルを下げるためにも補助対象を拡大する仕組みへ見直すことができないか、お伺いいたします。 給食への有機食材の導入には、量の確保や調理員さんの手間など課題が山積であることは 重々承知をしております。 そこで、一つ提案です。 まずは調味料から変えてはいかがでしょうか。 これは、より原理的な第一歩となり得ます。 みそ、しょうゆ、塩、砂糖、だしなど、基本的な調味料をより添加物が少ない自然に近い もの、オーガニックなものへ段階的に切り替えられるよう、県として何かしらの支援、後 押しができないか、お伺いをいたします。 最後に、食育の推進について。 食育は子どもたちの健康を守るだけではなく、心の成長や生きる力そのものを育てる大切 な教育でございます。 現場の生産者の方からお話をお伺いし、これまでの営業を中心とした学びだけではなくて、 農や環境にも目を向ける食農教育が必要だと強く感じました。 若狭町では、食農教育のモデル事業に取り組んでおられる方から、実際の子どもたちの変 化や保護者の理解の深まり、地域の農家さんとの交流など、たくさんの学びと手応えがあるというお話をお聞きしました。 このような取組が福井県全体に広がっていくことは、子どもたちにとっても地域にとって も大きな価値があると実感しております。 農業体験を通じて生産者の苦労や喜びに触れ、農業への関心を高めること、また環境負荷 軽減につながる有機農業の取組を知ってもらうことなどの食農教育を推進していくことに ついて鷲津副知事の見解をお伺いいたします。
鷲頭副知事
私からは、今の最後の食農教育の推進につきまして、お答えを申し上げたいと思います。 食農教育は非常に重要であると思っております。 食育にとどまらず、農や環境への理解を深め、子どもたちにとっては地域の自然やまた、 農業の魅力を伝えることにもなりますし、また地域にとっても、農業や環境を守る担い手 を育てるという意味で重要な取組だと考えております。 生産者の努力や喜びに触れる農業体験は、食への感謝を育みますし、また、農林水産物や 食品を選択する上での消費者の育成にもつながるというふうに思っております。 また、有機農業などの学びは、未来の食と環境を守る意識を育てるということでございますし、こうした活動は地域の絆を強め、そして持続可能な農業を実現する上で重要という ふうに認識しております。 県では、このため第4次のふくいの食育・地産地消推進計画に基づきまして、農林漁業体 験の充実や、また環境配慮への理解促進を進めているところでございます。 具体的には、市町が実施をします小中学校の農業体験活動への補助でありますとか、ふくい食と農の博覧会では、環境配慮型の農産物の展示なども行っているところでございます。 今後とも、生産者との交流をさらに広げてまいりまして、子どもたちが地域の自然や農業、 そして環境の大切さを学ぶ機会を充実させることで、持続可能な農業を支える食農教育の 推進に取り組んでいきたいと考えております。
稲葉農林水産部長
私から2点、お答えいたします。 初めに、有機米、特別栽培米の導入を支援する制度についてお答えいたします。 御指摘のとおり、昨年の秋から、標準的な方法で作られた米、いわゆる慣行米の価格が高騰しておりまして、現在も高止まりが続いているところでございます。 有機米や特別栽培米の価格も上がってはおりますけれども、慣行米との価格差は、米価高 騰前の令和5年に比べ、大きくは変わっていないという状況でございます。 このため、有機米給食推進事業における県の補助割合を引き上げる状況にはないものと認 識をしております。 また、この事業の補助対象でございますが、有機JAS認証米、または特別栽培米の認証 を受けたもの、もしくはこれに準ずるものとして県が認めるものとしております。このため、議員お尋ねの環境保全型農業直接支払交付金の有機農業区分の交付対象となっている米であって、有機JAS、あるいは特別栽培米の認証を受けていないものにつきましては、例えばですけれども、市町が栽培計画をチェックするなどしまして、認証を受けた米と同等のものであることを確認し、県が認めれば補助対象となり得るものと考えております。 続きまして、持続可能な農業を広げるための取組についてでございます。 新規就農者を含めた有機農家の育成、確保に向けまして、県では来年度から、まずは水稲 における有機農業特別栽培を体系的に学べる福井オーガニックグリーンアカデミーを開校 する予定でございます。アカデミーでは、基礎コース、有機コース、支援者コースを設けまして、受講者のレベル やニーズに応じて学べる環境を整備するとともに、県の普及指導員やJA職員等による支 援体制の充実を図ることとしております。 また、アカデミーの受講者が外部講師や県内外の有機農家などと交流し、情報交換できる 場を設けることも検討しているところでございます。 このアカデミーが有機農業推進の拠点として機能するよう、オーガニックアドバイザーなど関係者の御意見も伺いながら、開校準備を進めてまいりたいと考えております。 なお、有機野菜に関する人材育成につきましては、今後、県内における園芸分野での有機 農業等の広がりも見ながら検討してまいりたいと考えております。
藤丸教育長
私から、学校給食について3点、お答えをいたします。 まず、安定した質と量を確保した給食の提供への県支援についてお答えいたします。 小学校の学校給食無償化につきましては、国の実務者協議において、国費による全額負担 を断念し、保護者負担の軽減にとどまる可能性も出てきているという報道が先週ありまし て、また、昨日から本日にかけましては、約3000億円とも言われる財源を国と都道府県で 半分ずつ負担するよう、全国知事会の平井副会長に求めたという報道もなされたところで あります。 報道では国の支援額は月4700円程度とされておりまして、1食当たりの支援額が現行の食 材費に比べて低くなることが想定されますので、現在、無償化を実施している市町とそう でない市町では今後の財政負担に格差が生じかねず、また、保護者負担の有無をめぐって も混乱が予想されます。 さらに、国が約束した無償化について、この時期に突然都道府県に負担を求めるとう対応 にも強く疑問を感じております。 県としては、引き続き、新たな制度に係る国の動向を注視しながら、全国知事会や市町と 今後の対応を協議していきたいと考えております。 次に、地場産プラスワン給食の補助対象を地場産食材の変更にも拡大してはどうかという ことについてお答えいたします。 今年度から始めました地場産プラスワン給食ですけれども、月1回程度ですが、地場産食 材を使った副食を一品追加することによりまして、児童生徒が楽しみにしている給食の充 実を図るとともに、福井の自然、風土の中で育った地元の食材や生産者の思いに触れる機 会にしたいと思い、導入したものでございます。 実施した学校では、子どもたちから地元のメロンは甘くておいしかったといったような声 が上がっておりまして、好評を得ております。 地場産食材の利用につきましては、年度当初の学校担当者の研修会におきまして、より一 層の活用を呼びかけており、市町では食材の発注時に、まずは地元の市町産、次に県産、 次に国産、この順で食材を選定し、可能な限り地場産食材を献立に取り入れるよう努めて おられます。地場産プラスワン給食というのは単なる食材費の支援ではございませんで、子どもたちに メニューが一品増える日を楽しんでほしいという趣旨でございまして、食材変更への充当 は考えておりませんが、児童生徒がわくわくする機会が増えるよう、引き続き内容の充実 を検討していきたいと考えております。 次に、基本的な調味料を自然に近いものなどに切り替えられるような支援についてお答え いたします。 学校給食で使用する調味料につきましては、児童生徒の健康を考え、品質管理やアレルゲ ンの有無など、安全性などを確認して選んでおりまして、また、味噌、しょうゆなどはで きる限り地元のものを使うよう、地産地消にも心がけております。 一方、有機食材を利用した調味料につきましては、供給量が少なく割高になるなど、学校 給食で使用するには課題もございます。 こうした中でありますけれども、調味料は、各市町において地元の製造業者であることを 優先しておられまして、その中で給食の調理に適した数量の確保ができて、そして適切な 価格であるものを選んでおられます。 また、だしにつきましては昆布や鰹など天然の食材から取ったものを使用し、素材そのものの味を大切にする工夫をしております。 こうした取組を通じて、地元生産者の思いや加工などの生産過程、だしのうまみの相乗効 果などを学ぶきっかけとしております。 引き続き、市町と共に、有機農産物の意義も含めまして、福井の地場産食や健康的な食生 活への理解促進に努めてまいります。
中村議員
御答弁ありがとうございます。 昨日、国が急に4700円のうちの半額を県が負担できないかというようなことを知事会に説 明があったといって、報道でお聞きしましたが、そんな勝手なことを言われては困ると、 ぜひ国に全額負担でお願いしますと、ぜひ跳ね返していただきたいなという思いでござい ます。 ぜひよろしくお願いいたします。 その上で、例えば福井市ですが、今、小学校で月額5418円なんですね。 なので、国と県の支援の対象、月4700円では到底足りないというのが現状で、その差額を どうするのか、保護者が負担するのか、自治体がさらに負担するのか、大きな課題 が残っているなというふうに感じております。 ですので、ぜひそういったことが各市町で起こらないように、県としてさらなる支援をお願いしたいというような趣旨で申し上げさせていただきました。 なかなか難しいとは思っておりますが、ぜひ考慮していただければと思っておりますので、 よろしくお願いいたします。 地場産プラスワン事業についてですが、これは再質問にしようかなと思います。 今、地元のメロン、甘くておいしかったという子どもたちの声を聞いたと伺っておりますが、デザートとか、そういったプラスワンにしか使えない、例えば地場産の魚を積極的に 導入している自治体というのもありまして、調理員さんの負担も考えて、加工したお魚を 納入するということで、その分コストが高くなるというようなお話も聞いておりますし、 そもそも魚は高いので、最近、給食に取り入れることが少なくなったという自治体も聞いております。 さらには、より安い牛乳を仕入れるために県外産の牛乳を使わざるを得ないという、そん な状況まで出てきているという声もありました。 こういった現状、実情を考えますと、プラスワンだけではなくて、今使っている食材を地 場産に切り替えるのが先なのではないかなというふうに感じているところでございます。 これは、農業だけではなく、漁業・畜産業活性化にもつながりまして、地域経済を支える 非常に重大な、大事な視点になるというふうに考えております。 再度、本当にプラスワンにしないのかというような質問もしたいですし、本当にしないと いうことでしたら、現在、使用している食材を地場産に切り替えるためのどのような支援、 制度設計ができると考えられるのか、お考えをお示しいただきたいなと感じましたので、 再質問させていただきます。
藤丸教育長
まず、学校給食というのは御承知のとおり、市町が実施自治体ということで、 これまで取り組んできておられます。 こうした中でも、いろいろ食材費の高騰の中で、何らか県としての支援ができないかということを考え、今回、地場産プラスワン給食というのを始めさせていただいたところです。 これはデザートに限るといったような制限は設けておりませんので、地場産の食材を使ったメニュー、実は学校給食会が50品以上、そういったメニューを開発して提供しておりま すので、そうしたものを積極的に使っていただくとか、いろんな工夫の中で現場の実 態に合わせて御利用いただければと考えているところです。 あくまでも食材の入れ替えに使う食材費の補填ではないということだけ改めて申し上げさせていただきたいと思います。
中村議員
その制度設計を見直していただきたいという質問をさせていただいております。 量の確保とかそういったもの、質のプラスということになると思うんですけど、さらに質 を確保する、よいものにしていくという観点で、ぜひもう一度検討していただきたいなと いうふうに感じさせていただきました。 給食は地域農業にとって最も安定した販路にもなります。 ここを有機農産物の受皿にすることは、生産者の新規参入を増やし、結果として福井の農 地、農村を守る力にもなると考えております。 有機農業が増えれば、水質保全、環境負担の軽減、生物多様性の維持にもつながると考えております。 ぜひ、農業を守ることは未来を守る、福井の未来を守るということにもつながると思って おります。 ここは投資を惜しんではならないと考えております。 よりよい循環のために仕組みの構築というのを最後にお願いさせていただきまして、ハー ドルは高い事業でございますが、ぜひ有機農業を推進していただきたいとお願いして質問 を終わります。 ありがとうございます。